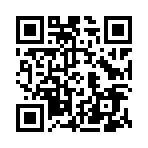2012年05月25日
ショーシャンクの空に 1994米 フランク・ダラボン

2度目の鑑賞です。
一度目は、展開への関心が高く2人の主人公
ヒーローと語り手の細かい心理には気がついていなかったことを痛感しました。
“希望”という今こそ身につけたいことと、
“希望”を持てる条件を、感動を通して語っています。
一度目の鑑賞では
ありえない脱獄を成功させたヒーローは、
それを用意周到に準備したととらえましたが、
それは彼の思いのひとつと知りました。
そこだけでも、十分に“希望を持つ条件”として、
* 希望は持つものではなく、持つに値する裏づけがあって初めて湧き出るもの
補足すると、持てる者に与えられるものであること
それを語る素晴らしい映画になります。
そこに、感動と戒めがあります。
けれど2回目の鑑賞では、それはエピソードのひとつであることがわかります。
ヒーローは、脱獄を行使することを目的としていたわけではありません。
希望をつなぐための手段として選んだのです。
だから前半の彼の行動があります。
“ショーシャンク刑務所を変える”それに尽くす彼の姿です。
彼は冤罪です。
けれど妻を死に追いやった自覚を(敢えてかもしれませんが)持ち、
その償いをショーシャンクで行っていました。
だから、脱獄のための影の努力は、
転ばぬ先の杖だったのです。
語り手を置くことで、そこを注目できたことで、わかりました。
ただ彼はヒーロー過ぎます。
だから語り手がもうひとりの主人公です。
ヒーローは、ショーシャンクを変えることで、
仲間に希望を与えます。
けれど、50年の服役で廃人となり社会復帰できない者、
彼と一体となって資格を得ることができた囚人が惨殺、
物語の半ばを過ぎても彼の想いは遂げられません。
最後に語り手が、凡人の代表として彼の想いを遂げます。
ここに現実感が起こります。
そして彼の、仲間との語りから、
“希望”は、死を覚悟してまでも、
得る価値があることというメッセージも受け取ることができました。