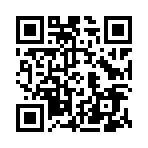2011年01月18日
伊豆の朝
同じ静岡に住んでいながら、
伊豆がこんなに暖かいとはしりませんでした。
たまたまかもしれませんが。
歴史を見ると駿河からは離れた、
ぜんぜん別の国だったのですから、
気候や風土が違う方が当たり前です。
海水浴と温泉というイメージだったのですが、
今回はだいぶ印象が異なりました。
年齢を重ねたせいもあるのでしょう。
2011年01月16日
よなよなエール
暮れに買い込んだお正月用ビールの最後です。
以前一度飲んだことがあり、好印象のビールです。
幻滅の錯覚は良くあることなので、
要注意で試飲しました。
コクがあることを改めて認識。
結論からこのビールは定番にしても良いということ。
少しいい間違えました。
この蔵のビールは定番にしても良いというのが答えです。
じっくりこの蔵のどれがお気に入りかを、
もう少し慎重に見極めたいです。
きっと夏に近づくとこの感覚を思い出すでしょう。
2011年01月15日
サンサン オーガニックビール
よなよなビールの1ブランドです。
ここのところこの蔵に凝っています。
このビールも以前飲んだことがあるのですが、
この蔵ということ、この蔵が他にどんなビールを
造っているかが解ってきました。
オーガニックは、
有機干し芋の生産者としても、
酒呑みとしても気になるところで、
オーガニックビールもけっして主流にはなりえないけれど、
頑張ってもっと流通して欲しいところです。
このビールは、価格もリーズナブルですし、
味もOKですから、オーガニックビールとして
もっと販売されるように思いますが、
発泡酒や第3のビールとビールの関係を考えると、
オーガニックというよりも、
ビール自体の地位のことを考えてしまいます。
2011年01月14日
薩摩ビール ヴァイツェンドュンケル
地ビールでヴァイツェンドュンケルが飲めるとは思いませんでした。
ドイツビールが好きです。色々なタイプがありますが、
輸入されている中で、ヴァイツェンドュンケルは1銘柄しか飲んだことがなかったからです。
ヴァイツェンドュンケルは、ヴァイスでありドュンケルですが、
その通りの造りであることが私的に満足です。
この蔵ヴァイスもOKだったのですが、
よなよなビールでもどのビールもOKです。
最近地ビールは当たりが続きます。
酒呑みとしても、日本人としても嬉しい限りです。
2011年01月13日
薩摩ビール ヴァイツェン
ドイツビールの1ジャンルのヴァイツェンを、
日本版で再現ていう感じです。
小麦ビール特有の甘みはヴァイツェンを思わせますが、
強い炭酸が日本版を感じます。
一時期雨後の竹の子のような地ビールブームがありましたが、
今残っている=売れている=人気があるのは、
やっぱり理由があるからでしょう。
ここのところ飲む地ビールはそれを感じさせます。
もう一本この醸造所(黄金酒造)のビールがありますが、
それも楽しみです。
2011年01月12日
よなよなエール 東京ブラック
タイプは「ポーター」です。
ロンドンスタイルのスタウトよりライトなビールとのことですが、
その通りの仕上がっています。
私的には、濃厚というほどではないですが、
十分な旨みがあります。
甘みと香りが程よいビールです。
この醸造所は、飲みやすいのと、
高次元のバランスをどのビールでも感じます。
2011年01月11日
國香 特別純米酒
菊姫ではない日本酒は、頂きものがあると飲みます。
ですから一年に何度かしか口にしません。
もちろん菊姫が一番と思っているし、
他の日本酒を飲む度にそれを確認できますが、
中には「これは」を思う日本酒もあります。
「國香(こっこう)」は「これは」までは行きませんが、
まあまあの一本です一言で言えば綺麗な酒です。
純米酒にとって綺麗という言葉は一概には
ほめ言葉ではありません。
綺麗の奥にしっかりとした、ワインで言う所のボディがなければ
ほめ言葉になりません。
五百万石が原料米ですが、その旨みを感じます。
菊姫とはテイストがかなり違いますが、
それなりに楽しめる日本酒です。
2011年01月10日
昭和45年11月25日 三島由紀夫自決、日本が受けた衝撃 中川右介

1960年代はかすかな記憶です。
その記憶を当時の映画で再び認識するのも好きなことの一つです。
三島由紀夫の印象は、映画「からっ風野郎」です。
この本を読むと映画の主人公以上の
知・力・考え・行動・洞察・予見力、があることがわかります。
誰よりもヒーローであり、役者であることも。
昭和で言えば30年代の日本は若く、エネルギッシュです。
希望が一杯です。
しかしその中にはたくさんの火種をくすぶらせていました。
その重大なひとつに三島由紀夫氏は、命をかけたのでしょう。
プラス、自分を神格化したかったことと合わせて。
2011年01月09日
2011初治作
胡麻豆腐
新年の第一品が胡麻豆腐でスタートは、
治作の原点の確認のようです。
好きなミュージシャンのライブの第一曲目が
とても気になるのと同じ心境です。
そしてもちろん治作の味です。
腐乳ごはん
ふたくちの量が惜しい量なのですが、
ここで我慢が一番美味しいと言い聞かせます。
胡麻豆腐に続き治作の伝統の味です。
感動的なアルバムのスタート2曲を堪能した感覚です。
お造り
ここでいつも停滞してしまい困ります。
アオリイカ、ヒラメ、赤身、中トロ
「いつもと一緒です」と言っだしてくれましたが、
いつもと一緒のレベルが高いことが特長です。
とろけるようなイカです。でも歯ごたえもあります。
ヒラメも食べ応えと甘みがバランスよし。
マグロはかなりの場数を踏んでますが、
この赤身・中トロは文句なく合格点です。
八寸
お正月の復習です。
これだけの品数はお造り以上に菊姫が
進んでしまいました。
ちなみにこの晩の菊姫は、12by山廃純米(山田錦)です。
強い酒プラス10年熟成です、
一口目だと料理に合うか心配になる酒ですが、
意外とオールマイティです。
それはこれだけの品数との組み合わせで確認できました。
さっきも触れましたが、ひとつひとつのレベルが高いのです。
全部の感想を書いていると全部「うまい!」でうまってしまいます。
盛りだくさんの料理と山廃純米熟成酒、
こんな贅沢はありません。
焼き物
迷いに迷いました。
候補は、
ブリの照り焼き、マナガツオの西京焼、牡蠣の天ぷら、正斎ふぐのから揚げ、鰆の西京焼、お肉
3人で行きましたから、
牡蠣、ふぐ、マナガツオを選んで回して食べました、
牡蠣:とっても大きい牡蠣です。ふっくらしています。
う~ん味わい深い!
マナガツオ:漬けかたで味が違ってくるのでしょう。
焼く前と印象が違います。濃く薄くしっかりとした旨みがついています。
その副産物が締まった身です。
マナガツオ:漬けかたで味が違ってくるのでしょう。
焼く前と印象が違います。濃く薄くしっかりとした旨みがついています。
その副産物が締まった身です。
ブリ:主張する魚です。
血合いから食べて、普通の身、あぶらがのる身、皮
と食べ歩きます。
どこもブリを主張します。後押しするのは、治作の下ごしらえです。
正月にはブリがつきものという地域があることは、
ブリを堪能すると納得します。
スッポン鍋
熱々なんてものじゃない!
スッポン鍋が目の前に現れます。
沸騰した鍋、
あまい香り、
熱々の熱が伝導します。
冬これだけ身体を喜ばせることがあるのでしょうか?
後ろ足を出してくれました。
肉も味わえる部位です。
付け合せの豆腐とネギがまたうまみを吸っています。
肉もすごいですが、汁のおいしさはこれに代わるものを思い浮かべません。
食べる前に味を想像してそれをはるかに上回ります。
スッポン雑炊
ただただ見た目は雑炊です。
何の目新しさもないのですが、
こればっかりは食べて感動してもらいたいです。
スッポンが身だくさん。
ネギと玉子が味も目も楽しませてくれます。
ここまででお腹一杯ですが、
なんと美味しいではないですか。
と食べました。
花マメお汁粉
上品なお汁粉です。
彩りにマーマレードが添えてあります。
このお汁粉をどうすればもっとお客さんが喜ぶかを
いつも考えているからこういう発想がでるのでしょう。
そして、できたてで出される美味しさ、
この白玉の美味しさは寿命が短い!今ここだから味わえました。
甘いのは美味しいのは当たり前。
どれだけその甘さを楽しめる甘さのデザートにするかが、
実ったお汁粉です。
2011年01月08日
丸太
奥のトラクターはこのあたりの干し芋農家のトラクターとしては、
一番大きなものです。
それと比べれば、丸太の大きさを感じてもらえるでしょうか。
この農家の知り合いの農家が「使え」ともって来たそうです。
どこから持ってきたのかは、わかりません。
当初貰った方の農家も困っていましたが、
皮を剥ぎ製材をはじめています。
農家って、何でも自分でやってしまう人が多いです。