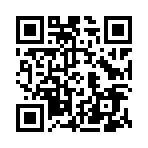2014年08月20日
2014年08月19日
芋虫対策

毎年この時期は芋虫が一番活発になります。
畑をサツマイモだけにすると、芋虫に狙われるので、
(もちろん農薬を撒けば別ですが)
畑内を多様にして芋虫対策をしています。
ある程度雑草は残し、畑周りにはクロタラリアを育ててそれをしています。
クロタラリアは背が高くなることから、
芋虫の侵入の妨げにもなることを期待しています。
2014年08月18日
2014年08月17日
追肥第一弾の効果

サツマイモの成長具合を観て、
EMボカシ肥料を入れた畑です。
つるの伸びが止まってきていましたが、
追肥効果で再び伸びてきました。
第二弾は、追肥というよりも、
サツマイモ自体を活性化させる液肥を葉面散布します。
2014年08月16日
草も伸ばしています

休耕畑に、土壌改善と緑肥の効果を期待して、
ソルゴを輪作で育てています。
この畑は、ソルゴばかりにするよりも、
雑草も生やせた方が良いという判断から、
ソルゴと雑草が半々で畑内で共存させています。
2014年08月15日
いずみが育ってきています

7月の時点では、奥の紅はるかに比べて、
かなり貧弱な手前のいずみでしたが、
紅はるかは早くつるが伸びきるので、
いずみが育ち、少々盛り返してきています。
しかし、元々の育ち方が紅はるかにはかなわないので、
このまま収穫までいきそうです。
2014年08月14日
味噌用の大豆

農園前の休耕畑にちょっとだけ大豆栽培しています。
この前は蒔いた途端にキジにいたずらされたので、
キジ対策して蒔きました。
大豆はもちろんそのままでも食材になりますが、
味噌には欠かせません。
本当はもっと作りたいのですが、
収穫が晩秋で、干し芋シーズンになるので、秋から、
ほんの少しの栽培にしました。
2014年08月13日
東京マダムと大阪夫人 1953日 川島雄三

時代観がしっかり確かめられて、でも普遍的な人間模様を映す傑作コメディです。
川島雄三監督らしくかなりシニカルに風刺も込められていますし、それが良いエッセンスになっています。
脚本も良くて、無駄がない、リズムも良いし、テンポ良く笑いが起こります。「幕末太陽傳」なみの完成度です。
その笑いも他愛のないことから、人間の根源に及ぶのものまであります。
そしてこの作品は悪人がでません。上辺の嘘や野次馬な嫌らしさはありますが、善人な庶民の物語です。
私的には人の嫌な部分を見せる「しとやかな獣」に共感していますが、こちらの描き方も共感できるし、川島監督の底力も感じます。
キャストも魅力があります。
庶民の物語なのですが、主人公の社宅夫婦の奥さんはどちらも名家の出身というところが粋で、物語に奥行きと夢を与えます。
高度成長期の一流企業のサラリーマンの暮らしぶりを中心に物語は進みます。
将来を期待される、伊東夫婦と西川夫婦は社宅の隣同士です。
この社宅は当時のサラリーマン家庭の縮図で、奥さん同士の見得の張り合いがあったり、嫉妬があったりといった当時の日常をしっかりと土台にしています。
社宅の名前は「あひるヶ丘」で実際にアヒルが社宅の敷地内にウロウロしています。このガーガー言うアヒル達は社宅内の奥さん連中そのもので、この演出は秀逸です。ぜひ観て欲しいとしか言い現せません。
会社内ではもちろん上手く切り抜けるサラリーマンもいれば脱落者も出てきます。社宅の付き合いは、会社の序列がそのまま社宅内の奥さんの序列になっているという、当時だったら誰もが頷く実態を織り込みながら、庶民感覚とは違う物語が挿入されていきます。
伊東の奥さんの美枝子(月丘夢路、夫は三橋達也)は東京の老舗の傘屋の出で、父親からの政略結婚の押し付けが嫌で飛び出しました。その妹康子(芦川いづみ)も同じ境遇で姉の下に逃げてきます。
西川の奥さんの房子(水原真知子、夫は大阪志郎)は大阪の昆布の佃煮問屋の出で、8人兄弟の末っ子八郎(高橋貞二)が仕事で東京に出てきます。この八郎がモテる役プラス気風が良いプラス飛行機乗りという設定で、サラリーマン社会とは違う世界の男です。付け加えますが、伊東も西川も真面目で有能なサラリーマンです。
そしてもうひとりヒロイン百々子(北原三枝)がいます。あひるヶ丘の会社の専務の娘で、明るくて屈託がない性格で康子と対照的です。
康子も百々子も八郎が好きになってしまい、美枝子は康子を自由に結婚させてやりたくて八郎と一緒になれるように、房江は専務の娘の百々子と八郎が結婚すれば旦那の出世になるとして当人同士を乗り越えて話を進めていくのですが・・・。
三角関係の行方と伊東と西川の出世話が絡んでいきます。
社宅ということもあり近所付き合いは大事で、隣同士で井戸を共用している環境からもそれがキーになっています。先に西川家が電気洗濯機を月賦で購入すると、房江は見栄をはります。また社宅内は噂話ですぐに持ちきりになりますし、それを仕切る者がでてきます。
これらは普遍の人の性でそれを面白おかしく描かれていますが、当時の近所付き合いが盛んという当時の世相もしっかりと封印されています。
奥さん同士がいがみ合ってしまう展開でも、旦那二人は割りと冷静なのも、演出でもありますが、これも良くみる光景で、だけど、現代からみると全体的に鷹揚な雰囲気がこんなところでも窺えます。
笑いが絶えない映画なのですがキャラクター設定が良いことも後押ししています。
二人の世話焼き奥さんと社宅の仕切り奥さん、そしてちょっと尻に引かれているような男達、八郎は正義感があって自由奔放だけど天然キャラ、美枝子(と康子)の父は頑固で江戸っ子、その奉公人達もユーモアがある(番頭の名前は「徳」で丁稚の名前が「定」、落語好きにはたまりません)、百々子は活発、康子は思いやりがある控えめの女性。
それらのキャラが上手くかみ合います。
目先の欲から、房子が嘘を付き、美枝子の手前伊東が嘘を付いてしまい、百々子と康子が傷つきますが、その事件も上手く回収します。(ちょっと皆が良い人過ぎるきらいはありますが、この映画の雰囲気にはあっています)
伊東と西川に出世競争がご破算になり、代わりに社宅の仕切り役が世代を変えるとしうオチも上手かったです。
とにかく私としては、始終楽しめる作品で、贔屓目かもしれませんが文句なしの映画でした。
2014年08月12日
グラマ島の誘惑 1959日 川島雄三

喜劇ではありますが、川島雄三なりの反戦映画です。
ちょっと物語として破綻しているところが惜しいですが、気持ちは十分に伝わってきます。
設定が面白いというか微妙です。
戦中、13人が無人島(グラマ島)で暮らすことになるのですが、そのメンバーは、皇族の兄弟(為久大佐と為永大尉)そして二人を補佐するバリバリの軍人の兵藤中佐、そして現地人のふりをしている脱走兵のウルメル、後は全員女性で、従軍慰安婦が6名、報道班で詩人のよし子、報道班で画家のすみ子、グラマ島にはかつて日本の基地がありそこで未亡人になった とみ子です。
為久は食べることと女のことしか頭にありません。為永は生真面目ですが同じく生活力はありません。兵藤は皇族二人には従順ですが、女達の前では威張りちらします。
皇族や軍人には無条件に従うものだという教育をされてきた慰安婦達は、3人の男達に仕えることに何の疑問も持ちません。
とみ子は元々グラマ島に住んでいましたから、ウルメルの援助を受けながら、軍人3人と慰安婦達とは距離を置きます。報道班の二人の女性は男達に反抗的なので厄介者扱いされます。
そんな戦前の軍事システムが、二人の女性の目論見で(慰安婦達に今の生活はあまりにも理不尽であることを説いて)女性全員で反乱を起こし、島を民主社会にします。このあたりがこの映画の一つのテーマです。
でも川島演出は一筋縄では民主化を成功させません。一度は鎮圧された男共は武器を手にして女性を抑えることに成功します。これもかなりブラックな暗喩です。
その後武器はウルメルが奪ってまた民衆主義が機能して6年の月日が流れます。島の近くでは水爆実験があります。それと同時に終戦していたことがわかりアメリカ軍に助けられて、日本編になります。
日本編でも風刺が続きます。経済的に復興している日本で沖縄返還の運動も行われいますし、皇太子殿下の結婚にも浮かれいます。
その中でグラマ島から帰ってきた為久は家族と恋人に捨てられ、為永は事業が上手くいかない、すみ子は「グラマ島の悲劇」という本を執筆しベストセラー作家になりますが、かつての仲間からは反感を買います。慰安婦達は沖縄で商売しようとして逮捕されます。
なんだかグラマ島の生活の方が幸せだったように映ります。
そのグラマ島も水爆実験の場になってしまいます。そこでラスト。
非常に辛辣な隠れメッセージに満ちている映画です。
ただ当初ブラッックな笑いだったのが笑いに笑えない感じになります。
そして、女性達の描かれ方が面白いのですが、それと主題が合っていないような感じでまとまりがない印象になります。
しかしながらこれも川島雄三でなければ撮れない映画だということを感じる個性的な作品であることは間違いありません。
2014年08月11日
まごころ 1939日 成瀬巳喜男

二度目の鑑賞です。
一度目の鑑賞では、二つの家族を通しての深くて優しい人間模様の映画、
そして、プロパガンダ色がありながらそれをも逆手に取って、主題を語っている映画と感じました。それは今回も同じなのですが、二人の子供を通しての親三人の成長物語だということがテーマだと強く思いました。
金持ちの夫婦の敬吉と敬吉夫人の娘が信子、貧乏な未亡人の蔦子の娘が富子、この5人の物語です。
かつて敬吉と蔦子は愛し合っていたましたが、敬吉が金持ちの婿養子に行きやすいために蔦子が身を引きます。敬吉夫人は気立てが良い蔦子に嫉妬しています。身を引いた蔦子の夫はとんでもない飲んだくれでしたが、蔦子は健気に尽くし、独り身になっても内職で実の母親と富子を立派に育て上げていました。が
ある日、敬吉を蔦子の過去のことを知った子供二人は、複雑な気持ちになります。
そんな時に、信子がケガをしてそれが原因で、敬吉は蔦子とばったりと出会ってしまいます。
当然なにも起きませんが、合ったことを知った敬吉夫人は嫉妬から敬吉を責めます。
けれど誤解は解けて。という流れです。
小学生6年生、大人一歩踏み入れた女の子二人が、子供心に親を想う気持ちと、深い友情で結ばれていることと、様々な体験から大人になっていく姿が汲み取れます。
それだけで、十分に心を癒される映画で、また、時代から周りの人びとのために(お国のためにも含まれます)という優しさも窺えるし、亡き父親が飲んだくれだったことの傷心する富子とそれを負い目に、そして不憫に思い、蔦子が富子を愛する姿にも、それを汲んで富子が自立しようとする姿にも、感動します。
それを踏まえて、親たち3人が成長して、結果敬吉はなんのわだかまりもなく出征するのですが、出征はともかく、3人共過去にケリをつけたことが印象的でした。
敬吉夫人は一番わかり易く、嫉妬していた自分を恥じて改心します。物語の流れからすんなりです。
敬吉は、蔦子とはもちろん何かがあるわけでもないですし、蔦子を結婚しなかったことに後悔しているわけではありませんが、婦人に対して、もうこの女はこのまま(自分にとっても娘にとっても良い女にはならない)というあきらめていた自分を、もちろん愛していないわけではないけれど、距離をおいていた関係性を改めます。
そして蔦子ですが、二度目の鑑賞で蔦子の成長を一番注目しました。
蔦子は、文句なしの女性です。
働き者で、ダメ夫にも尽くしていたし、敬吉の婿に行きたい気持ちを察して身を引くという自分を犠牲にしても他人のためと考え、しかも、それを心の底から願いとしてできる女性です。富子はクラスで一番の優等生なのですが、それこそ、蔦子の姿を観て育ったからに他なりません。
そんな蔦子ですが、富子に真実を、父親が飲んだくれだったことを話していませんでした。もちろん富子を傷つけたくないからですが、いつかは伝えなければということ、もちろん敬吉は愛し合っていた仲だったことも含めて、富子に話すことを「いつか」として躊躇していたのです。今回ちょっとしてきっかけで話さなければならなくなったのですが、やはり話してたくないことでした。
それは敬吉との関係は潔癖で、誰に何を言われることはないのですが、富子に話せない自分を負い目としていたのです。
その自分にケリを付けたのです。
富子の台詞に「おかあざんもさよならしなくちゃね(敬吉と)」があります。
この言葉はこの物語は蔦子の成長物語でもあったことを語ります。
三人三様の成長を映した映画で、心が清くても、ちょっと貧しくても、前に進むことは気高く価値があることを示していたことを感じました。